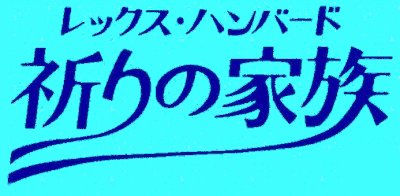親愛なる祈りの家族のみなさん。
インドにマーク・バンテーンという宣教師がいました。日本ではあまり知られていませんが、インドではマザーテレサと並んで大変尊敬されていた人です。貧しい人々のために孤児院や病院や学校を建て、食べ物にもありつけないで町にあふれていた人々のために毎日無料で給食をしていました。私は現地でその給食の情景を見ましたが、あまり大勢の人が道に並んで給食の順番を待っていたため警察官が出て警備しなければなりませんでした。
マーク・バンテーンはカルカッタを中心にしてインドの東部で数年前まで元気に活動していました。私は彼の話を2度ほど聞く機会に恵まれましたが、とても感動しました。
彼の献身的な奉仕活動に心を打たれた一人のインド系アメリカ人の実業家が自分の会社も私財も全てを投げ出して、インドの人々に奉仕する決意をしました。それがタイタス博士です。
タイタス博士はおもにインドの中東部の田舎で活動しました。子どもホームや学校や教会や病院を次々に建て、大きなクリスチャンの村を造って貧しい人々に教育の機会を与え技術を習得させ信仰に導いて、彼らの将来に大きな希望を与えました。
マーク・バンテーンやタイタス博士の働きは彼らが世を去った後も続いています。祈りの家族の中には今でもタイタス博士の働きに協力して子どもホームをサポートしている方が何人もおられます。とても素晴らしいことだと思います。このような業績はいつまでも残ります。病院や学校が残るからではありません。確かにその活動も末永く残りますが、それ以上に、愛と思いやりの心を受け取った人々の中に大きな影響が残り、それが周りの人々や次の世代へと受け継がれていくからです。
私はマーク・バンテーンがインドのために献身するきっかけになった時の話を今でも忘れません。町で物乞いをする子どもたちの中に足や手に不自然な障害を持っている子どもが目立っていたので、事情を聞いてみると、貧しい親たちがありたけの知恵を絞って「子どもを不自由な体にしておけば、物乞いをする時、誰よりも多くの同情を受けて何とか生き延びることが出来る」と考えたからでした。
私はその話を聞いた時涙が止まりませんでした。そんなことがあっていいのだろうかと思いました。けれども、彼らにとってはそれが子どもたちの将来を思う精いっぱいの知恵だったのです。
もしかしたら私たちの行なっていることも神の前にはあまり違っていないかもしれません。
子どものために少しでも良い学校、良い会社、良い結婚相手、良い家、そして良い老後をと、地上のことには精いっぱい心を配ります。そのような気配りが全く無意味とは思いません。けれどもそれだけが人生ではあまりにも空しいではありませんか。自分に何が出来て、何がいつまでも残り、永遠につながるような生き方になるかを、子どもたちに身をもって示すことの方がはるかに大切です。人生は他の人から何をもらえるかよりも、他の人のために何が出来るかに意味があるからです。人から上手にたくさんのものをもらうことよりも、人に何かを与えることが出来る人生に親が真剣に取り組むなら、その姿は何よりも大きな贈り物となって子どもたちの心にいつまでも残るのです。
このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また、主イエスご自身が、『受けるよりも与えるほうが幸いである。』と言われたみことばを思い出すべきことを、私は、万事につけ、あなたがたに示して来たのです。」(使徒の働き20章35節)
私たちは受け取るプロを育てるよりも、与えるプロとしての良い手本になるべきです。
新約聖書の中に一人の女の人の記事が書かれています。その人は高価なナルドの香油の入った壺を割ってそれを全部イエスの体に注いでイエスの葬りの記念としました。当時の習慣では、結婚の準備中の女の人は全財産をはたいて高価な香油を買い壺に入れて持っていました。ところがその人はそれをイエスの上に全部注いでしまったのです。その後、この人が幸せな結婚が出来たのか、どのような家庭を持ってどのように生涯を送ったのか、何一つ聖書には書かれていませんが、イエスが言われた通り「この人のしたことはいつまでも語り告げられ」世界中に知られて今も人々の心に残っています。(マタイ26章7-13節)
「イエスはもうこの世にはおられないのだから、私たちはもはやこの女の人のように直接イエスに何かをして差し上げることは出来ない」と思われるかもしれません。けれども、イエスはこう言っておられます。
「まことに、あなたがたに告げます。あなたがたが、これらのわたしの兄弟たち、しかも最も小さい者たちのひとりにしたのは、わたしにしたのです。」(マタイ25章40節)
私たちがイエスのために何かをしたいと願うなら、助けを必要としている人々、お返しも出来ない、最も小さな者たちの一人に何かをしてあげることです。喜ぶ者と共に喜び、悲しむものと共に悲しむことです。そのような機会は私たちの周りにいくらでもあります。その一つを実行するだけで、イエスは「わたしにしてくれた」と言ってくださいます。
イエスはご自分が何かをしてほしいのでそう言われたのでしょうか。そうではありません。むしろ、私たちのためです。私たちにいつまでも残る充実した人生を得てほしいと願ってそう言われたのです。貧しい人々や恵まれない子どもたちは、それによって助けられ大いに喜ぶことも確かです。しかし、それ以上の喜びを味わうのはそれを行なった人自身と、その人が成長する姿を見ておられる神です。
「わたしがこれらのことをあなたがたに話したのは、わたしの喜びがあなたがたのうちにあり、 あなたがたの喜びが満たされるためです。」(ヨハネ15章11節)
生きているということは自分の周りにさまざまな影響を及ぼしているということです。それが人々を励まし、助け、感動を与え、いつまでも心に残り、受け継がれて行くものであってほしいと思います。しかし、何よりも先にその行いはあなた自身の中に一番大きく働き、喜びがいつまでも残り、末永く続くものとなるのです。神ご自身がそれを見て喜んでくださるからです。
あなたは愛されています。
レックス・ハンバード世界宣教団
日本主事 桜井 剛