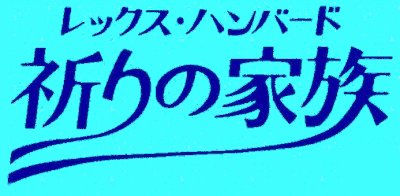祝福のメッセージ
福音書にあらわされたキリスト
No.201003
③ キリストの誕生の預言と処女降誕の信仰
イエス・キリストの誕生はすでに旧約聖書の中で繰り返し預言されています。
ひとりのみどりごが、私たちのために生まれる。ひとりの男の子が、私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は「不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君」と呼ばれる。(イザヤ9章6節)
主みずから、あなたがたに一つのしるしを与えられる。見よ。処女がみごもっている。そして男の子を産み、その名を『インマヌエル』と名づける。(イザヤ7章14節)
エルサレムを建て直せという命令が出てから、メシヤなるひとりの君が来るまで、、、(ダニエル9章26節)
ベツレヘム・エフラテ。あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから、わたしのために、イスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは、永遠の昔からの定めである。(ミカ5章2節)
新約聖書は、マタイとルカが福音書の中でイエス・キリストの誕生の次第をこう記録しています。
イエス・キリストの誕生は次のようであった。(マタイ1章18節)
主の使いが夢に現われて言った。「ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリヤを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリヤは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。」(マタイ1章20、21節)
御使いは、はいって来ると、マリヤに言った。「おめでとう、恵まれた方。主があなたとともにおられます。こわがることはない。マリヤ。あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい。あなたはみごもって、男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子はすぐれた者となり、いと高き方の子と呼ばれます。」(ルカ1章28-32節)
この出来事は、キリスト教の基本的な信仰告白の一つとなっていて「キリストの処女降誕」と呼ばれ、使徒信条の中に含まれています。
「我は主イエス・キリストを信ず。主は処女マリヤより生まれ、・・・」(使徒信条)
処女降誕は、人々のすぐ近くで起こったことであり、身近な人々もそれを知っていたため、それを聞いた当時の人々は何の疑いもなく事実として受けとめていました。けれども、この超自然的な出来事も、何年か過ぎて目撃者や証人たちが世を去るに従って、信じない人々が出始めます。さらに百年、千年とたつと、処女降誕をどう信じるかについての大きな神学的論争となりました。
けれども、福音書では、そのほかの奇跡と同様、イエス・キリストの処女降誕についても事実を記録するだけで、人々を説得しようとはしていません。これも神のご計画の中にあったことに違いありません。事実を目で見て、証拠を見せられてから信じるのでは本当の信仰とは言えません。確かな証拠を見てはいないけれど、神のことばを信頼して、信じることが本当の信仰と言えるのです。
福音書の中ではマタイとルカだけが、天使ガブリエルがマリヤのもとを訪れてこれから起こることを予告した事実と、マリヤの心の中に起きた不安と喜びの交錯したありさまを記録しています。
「ほんとうに、私は主のはしためです。どうぞ、あなたのおことばどおりこの身になりますように。」(ルカ1章37節)
夫ヨセフも悩み、心配はしましたが、これを信仰によって受け止めていました。
夫のヨセフは正しい人であって、彼女をさらし者にはしたくなかったので、内密に去らせようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現われて言った。「ダビデの子ヨセフ。恐れないであなたの妻マリヤを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリヤは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。」ヨセフは眠りからさめ、主の使いに命じられたとおりにして、その妻を迎え入れ、そして、子どもが生まれるまで彼女を知ることがなく、その子どもの名をイエスとつけた。(マタイ1章19-25節)
全知全能の神は、私たちの知恵を遥かに超えたご計画をお立てになりました。そのご計画によって、神から離れてしまった人類を罪と滅びから救うために特別な出来事をお用いになって、イエス・キリストをこの世に送られたのです。
この方を信じる者だけが、永遠の命を持つためです。
神は、実に、そのひとり子をお与えになったほどに、世を愛された。それは御子を信じる者が、ひとりとして滅びることなく、永遠のいのちを持つためである。(ヨハネ3章16節)
いよいよ、イエス・キリストの生涯を通して人類の歴史の中に神の語りかけが始まる大舞台が整いました。私たちも、心を備えてその語りかけに耳を傾けてまいりましょう。