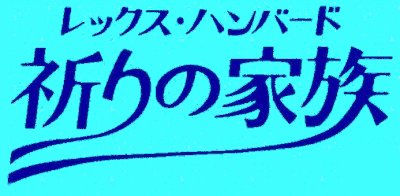祝福のメッセージ
No. 201806
イエスは必ず父なる神の臨在と共におられる
さて、イエスの両親は、過越の祭りには毎年エルサレムに行った。イエスが十二歳になられたときも、両親は祭りの慣習に従って都へ上り、祭りの期間を過ごしてから、帰路についたが、少年イエスはエルサレムにとどまっておられた。両親はそれに気づかなかった。イエスが一行の中にいるものと思って、一日の道のりを行った。それから、親族や知人の中を捜し回ったが、見つからなかったので、イエスを捜しながら、エルサレムまで引き返した。そしてようやく三日の後に、イエスが宮で教師たちの真中にすわって、話を聞いたり質問したりしておられるのを見つけた。聞いていた人々はみな、イエスの知恵と答えに驚いていた。両親は彼を見て驚き、母は言った。「まあ、あなたはなぜ私たちにこんなことをしたのです。見なさい。父上も私も、心配してあなたを捜し回っていたのです。」するとイエスは両親に言われた。「どうしてわたしをお捜しになったのですか。わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのですか。」しかし両親には、イエスの話されたことばの意味がわからなかった。それからイエスは、いっしょに下って行かれ、ナザレに帰って、両親に仕えられた。母はこれらのことをみな、心に留めておいた。 (ルカの福音書2章41-51節)
新約聖書の中でイエスが語られたことばを直接の引用している最初のことばはイエスが12歳の時のことでした。
多くのユダヤ人たちは、エルサレムの周りのパレスチナ地方に住み、季節ごとに、旧約聖書が教えている数々の行事に参加しました。その中の大切な行事の一つに、過ぎ越しの祭がありました。それは、イスラエル民族が奴隷の状態から解放されてエジプトから出る前の夜、エジプト中に起こった災いがイスラエル人の上にだけは起こることなく過ぎ越して行ったことから、それを記念して毎年行われてきた行事です。イエスが十字架にかけられたのもその記念行事の最中でした。
過ぎ越しの行事に参加するためにマリヤとヨセフも12歳になられたイエスをともなって、親戚の人々と共にガリラヤからエルサレムに出かけて行きました。
過ぎ越しの行事は何日にも及びますが、それが終わって一同が帰路に着いた時のことでした。イエスが一行の中にいないことに気が付いたのです。両親はあわてて探しまわりましたが見つかりません。探しながらエルサレムまで戻ってみるとどうでしょう、イエスは宮にいて、律法学者たちの真ん中に座って話し合っておられたのです。
律法学者というのは旧約聖書の教えに精通していた、ユダヤ人の指導的な立場にある人たちでした。田舎から来たヨセフの家族にとってはとんでもなく偉い人たちです。けれども、イエスは律法学者たちの真ん中にいて話を聞いたり質問したりしておられました。律法学者たちはイエスの賢さにおどろいていました。
律法学者たちは将来、成人なさったイエスと激しい議論をすることになるとは、その時は想像もしていなかったことでしょう。
心配して迎えに来た両親に対してイエスはこう言われました。
「どうしてわたしをお捜しになったのですか。わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのですか。」
帰路に両親や親せきの人びとと一緒にいるはずだったイエスがいなかったので、両親があわてて探したのは当然のことでしたが、「わたしが必ず自分の父の家にいることを、ご存じなかったのですか。」とはどういう意味で言われたのでしょう。賢く成長し始めたイエスが「もういつでも一人でお父さんの家に帰れます」と言われたのたのでしょうか。
福音書の著者ルカはイエスがそれとは違う意味で言われたということを示唆するために、「しかし、両親には、イエスの話されたことばの意味がわからなかった」と付け加えています。もっと深い意味があったことをルカは感じていたのです。
では、自分の父であるヨセフの家のことではないとすると、それはイエスが律法学者たちと話をしておられた神の臨在を象徴するエルサレムの神殿の宮の中という意味でしょうか。けれども、神殿を自分の父の家と言うことには重大な意味があります。誰もそんなことを言える人はいません。神の子だけに言えることです。
両親に連れられてエルサレムに上り、まいごになったのではないかと両親を心配させておられたイエスですが、すでに神の子としてのご自分の使命を感じておられたのです。それゆえ、ご自分の父の家、すなわち、神の臨在を象徴する場所である神殿の宮の中にいることはごく当たり前のことであるということを、両親に知らせておられたのです。
12歳になったばかりのイエスですが、すでにご自分の使命を自覚しておられたのです。一家の長子として両親に仕えながらも、神の子として全人類を罪から救うために、どのような生涯をおくることになるのかを、どんな気持ちで受け止めておられたのでしょう。
聖書は、少年イエスが律法学者たちを驚かせるほどの知識を持っておられたこと以外には詳しい記録はありませんので、30歳になって、公に宣教の働きをお始めになるまで、一見平凡な生活をおくっておられたかのように思われますが、この出来事を通して、イエスが日々ご自分の使命を自覚しつつも、両親に仕えておられたことを、うかがい知ることが出来ます。