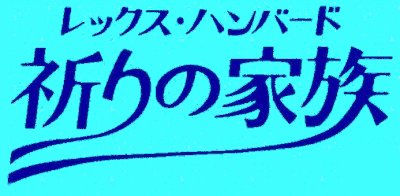No. 201910 山上の垂訓I
心の貧しい者は幸いです。
天の御国はその人たちのものだからです。
その群衆を見て、イエスは山に登られた。そして腰を下ろされると、みもとに弟子たちが来た。そこでイエスは口を開き、彼らに教え始められた。
(マタイの福音書5章1節2節)
今回から、山上の垂訓からイエスの教えを学んでまいります。それはガリラヤ湖畔のカペナウムでおこなわれました。私は何年も前にそこを訪れたことがあります。ガリラヤ湖に面した、なだらかな丘が続く静かな田舎でした。イエスが丘の上から大勢の群衆に教えておられたことが想像できる場所です。
そこに八角形の建物があって、壁の一つ一つに、「幸いなるかな」で始まるイエスの八つの教えが書かれていました。今回はそれを学んでまいります。
山上の垂訓におけるイエスの教えの特徴は、ほかのところでも同様ですが、世の常識とは違っていて、時には全く逆のように思えることがあります。ですから、もし私たちがイエスの教えに完全に従いたいと思う時にはこの世の常識を超えた生き方をしなければならないのです。もし、そんなことは不可能だと感じるとしたら、この世における私たちの生き方は、すでに神の国における生き方から、かなり離れてしまって、この世の生き方に近くなっているのかも知れません。
私たちが本当にイエスに従って、神の国を目指したいと願うなら、しばしば世の標準とは違った価値判断が求められます。イエスは、この世が敵としている者を愛し、人から偉いと思われて仕えられる者ではなく、むしろ人に仕える者になれと教えておられます。
当時ユダヤ人の指導者たちは、旧約聖書の律法の教えに精通していました。それを誇りとして、自分たちがその教えに従って行動することよりも、上に立って人にそれを教え、それを守るかどうかを監視することが自分たちの役目であり特権であると思っていました。彼らにとって、イエスは自分たちの権威を危うくする存在だったのです。
イエスが教えておられる神の国の姿に近づくためには、まず、ここで教えられていることを一つ一つ私たちの生き方に当てはめてみる必要があります。
心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。(3節)
心が貧しいとは霊的にへりくだって自分には何も誇るものはないことを認めている人のことです。イエスが言われる心の貧しい人とは、誇らず、他の人を敬い、引き立てる人のことです。もしそういう人がそばにいたら、私たちの心はどんなに和らぐことでしょう。神の国がその人の内にあるからです。
悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。(4節)
なぜなら、たとえ今悲しむようなことがあっても、つらいことがあっても、それは一時的であって、やがて大きな慰めに代わることが、神の国を目指す者のためにイエスご自身が約束しておられるからです。そして、神の慰めを経験した人は、悲しんでいる人を慰めることができます。
柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。(5節)
この世では柔和な人は弱い人と見なされて、押しのけられるかも知れません。しかし、神の国ではそういう人こそ祝福された人で、その受ける報いは大きいのです。「その人は地を受け継ぐ」というのです。
地は当時の人にとって必要な全てを産出してくれるもの、生きるよりどころでした。イエスが言われたのは、現実の土地のことではなく、私たちに必要な霊的な祝福の源、霊的ないのちのよりどころ、と言ったらよいでしょうか。
イエスのどのことばも、そこには、どんな生き方が神に喜ばれ、永遠の祝福につながるかを教えています。それは、信仰を土台とした生き方です。
義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。(6節)
私たちは義を求めているでしょうか。これが正しいと分かっていても、それが自分の損になったら、目をつぶってそれを避けるでしょうか。熱風が吹き荒れる砂漠で水を求める人のように、激しく義に飢え乾く人を、神は求めておられます。その人は満ち足りる、とイエスは約束なさいました。
山上の垂訓の中でイエスが保証しておられる約束は、今、幸せであるとか今、豊かであるという、この世が与える一時的なものではありません。また、地上で多くの人が願っている、他の人との戦いに勝って上に行くことでもありません。この世の豊かさや繁栄や、名誉ある地位と呼ばれているものでもありません。どんなことによっても奪われたり失ったり消えたりすることのないものによって満ち溢れるまでに、主は私たちを満ち足らせてくださるのです。
― 続く -