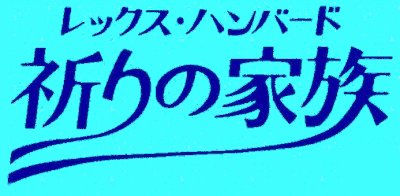No. 201911 山上の垂訓Ⅱ
あわれみ深い者は幸いです。
その人たちはあわれみを受けるからです。
山上の垂訓(マタイ5章)の中から、今回は八福の教えの後半を学びます。
あわれみ深い者は幸いです。その人たちはあわれみを受けるから。(7節)
前回も学びましたが、山上の垂訓に限らずイエスの教えの特徴は、世の常識とは違って、時には真逆のように思えることがあります。ですから、もし私たちがイエスの教えに従いたいと思う時はこの世の常識にとらわれないようにしなければなりません。
今回は、私たちがこの世で経験する困難や辛い出来事を、まっすぐに掘り下げることによって、そこから、より大きな恵みを掘り起こすことができることを教えています。
あわれみ深いとは、ただ単に憐れに思うだけでなく、その事実を自分自身に当てはめてその人の状況をその人の立場になって思うことです。折しも、自然災害によって大勢の方が被害を受けて今も辛い毎日を送っておられます。私が、「気の毒だねえ」言うと、「それはあまりにも他人事のように聞こえますよ」と、妻にたしなめられました。確かにその通りだと思います。あわれみ深いとは、ただ単に気の毒に思うことではありません。その状況を自分のことのように深く心に受け止めることです。イエスは、そのような人は必ず、同じように深い憐れみを受ける、と保証しておられるのです。
心のきよい者は幸いです。その人たちは神を見るから。(8節)
いったいどのような人が、「心のきよい者」と言えるのでしょう。パウロは、「義人はいない。ひとりもいない。」と教えています。(ローマ3章10節)
ここでイエスが言われる、「心のきよい者」とは一般に聖人君子と言われている人のことではありません。もともと、イエス以外に罪のない人は一人もいないからです。
イエスは言われました。「子どもたちをわたしのところに来させなさい。止めてはいけません。神の国は、このような者たちのものです」(ルカ18章16節)イエスが言われる「心のきよい者」とは、幼子のように素直で純粋な心を持つ人のことです。そういう人こそ、神を素直に知ることができる人です。
平和をつくる者は幸いです。その人たちは神の子どもと呼ばれるから。(9節)
いつの時代でも、平和であることは人々が一番願っていることです。平和は国と国との争いをなくすことだけではありません。一人一人の心に平和を愛する気持ちと行動力がなくては始まらないのです。
今ほど平和が強く求められているときはありません。権力や支配力を奪い合う一握りの人々のために、何も関係のない人々が命を失っています。そのような中で平和を作ることは並大抵のことではありません。キリストの愛にならって、まず自分を捧げて自分の周りから、平和を作り出すために行動する人になるべきです。私たちの家庭から、隣り近所から始めましょう。そういう人は神の子どもと呼ばれるにふさわしい人です。
義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。(10節)
前回、私たちは義に飢え渇く者たちは満ち足りることを学びました。(6節)もし、私たちが積極的に正しいことを求めてそれを行なっているなら、必ず心が満たされます。けれども、私たちはいつも義を求めているでしょうか。正しいと分かっていても、それが自分の損になると思ったら、それを避けようとしませんか。良い事を実行に移すのは時には至難の業です。そのために困難に耐え、迫害を受けるとしても、それは幸いであるとイエスは言われるのです。
自分は正しいことをしているのに、なぜ人は分かってくれないのだろうと思うことはありませんか。正義かどうかの正しい判断は神がなさいます。
正しいと思っていても実際には正しくない場合もあります。そのような時は、たとえうまくいかなくても、自分にとって良い反省の機会になると思って謙虚にその事実を受け止めて、やり直せばいいのです。
地上においては全てが順調にいく、ということはありえません。だからこそ私たちは天の御国を求めるのです。けれども、正しいことをしていても、それが受け入れられなかったり、迫害されたりすることもあります。あらゆる観点から正直に正しいことをしていると思っても、反対を受けたり、迫害を受けたりします。「そのような時のあなたは、幸いな人なのです」。イエスがそう言っておられるのですから、恨みを持ったり投げ出したりしてはいけません。必ずあなたにとって益となります。自分が間違っているのか、それとも、相手が間違っているのか、簡単には分らないことがしばしばです。謙虚になって全てを神にお任せしましょう。神が全てを知っておられるのですから、神があなたに報いてくださいます。イエスは「失望してはいけません。天の御国はあなたのものだからです。」と言っておられます。