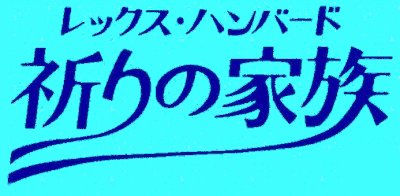No. 200109
創造と進化
初めに、神が天と地を創造した。(創世記1章1節)
「創造と進化」と言うと、すぐに短絡的に「非科学的だ」とか「進化論は間違いだ」と極端な論争に走ってしまいがちです。
科学は完成してはいませんが、間違いでもありません。また、もし間違いに気づいたときはそれを改めることができます。それが正しい科学のありかたです。
一方、聖書の記述も決して科学と矛盾してはいません。
もちろん、科学者と自称する人々の中には、科学を盲信するあまり科学的ではなくなってしまっている人もあります。けれども、科学に対して正しい理解を持っている人は聖書の記述に何の問題も感じていませんし、聖書に対する正しい理解の仕方をしていれば科学的な事実が役立つものならそれを受け入れ、安心して活用することができます。
私は科学者が同時に真剣なクリスチャンであるという多くの実例を知っています。私が大学で学んでいたときの物理学の教授の一人がクリスチャンでした。書籍やインターネットを通して科学と聖書の記事の美しい調和を熱心に伝えている科学者も知っています。
聖書を中途半端に学んで聖書を論じたり、科学を中途半端に学んで科学を論じたりすると、先入観にじゃまされて、とんでもない勘違いをしてしまいます。「神が天地を造られたのだから進化論を認める科学は誤りである」と言ったり、「動物も植物も進化しているのだから神が造ったと言う聖書は間違いである」と断言してしまうのです。
それは、ちょうど「大阪城は豊臣秀吉が作ったのではない」と言うようなものです。確かに秀吉は農家の出身ですから、農耕の技術は知っていたでしょうが、木を削り材木を組み合わせたり、白壁を上手に塗ったり、石を刻み重ねて城壁を築いたりすることは出来なかったことでしょう。しかし、何百人の大工や石工や左官が集まっても、設計をさせ、材料を買うお金を提供し、命令を下す人がいなかったら大阪城は自然に出来るものではありません。秀吉の権力と指導力と財力がそれを可能にしたのです。
そのとき、神が「光よ。あれ。」と仰せられた。すると光ができた。(創世記1章3節)
何もなかったところから宇宙ができ、光が存在するようになるという難しい課題に取り組み、その理論や経過を研究するのは科学の役割です。
一方、このことをなさった神の偉大な力に感動し、神をあがめ礼拝するのは信仰の分野です。それが同時進行しても何の問題もありません。むしろ、人類はそのどちらも必要としているのです。
神が、「地は植物、種を生じる草、種類にしたがって、その中に種のある実を結ぶ果樹を地の上に芽生えさせよ。」と仰せられると、そのようになった。それで、地は植物、おのおのその種類にしたがって種を生じる草、おのおのその種類にしたがって、その中に種のある実を結ぶ木を生じた。神は見て、それをよしとされた。(創世記1章11,12節)
創造と進化を論じるとき注意しなければならないことがあります。
- 1. 聖書と科学はそれぞれ違った土俵に立っていることを理解すべきです。
聖書は長い歴史の背景の中から、その背後に神の力が働いておられる結果として生まれてきた、神から人類の心の奥底へ語りかけることばです。科学の教科書ではありません。
国語の教科書に「太陽が赤々と西の空に沈んで行った」と書いてあっても、「太陽は動いてはいない、地球がまわって太陽が見えなくなるのだ」と言って国語の教科書を非難する科学者はいません。
- 2. 私たちはすべてを知っているわけではないのです。
科学は進歩していますが、新しい疑問が残り、未知の世界はますます広がってきます。どんな理論も完全に証明出来るまでは仮説であり研究の段階です。
私たちは聖書をよく読んでいるとは言っても、聖書に書かれている真の意味をすべて完全に把握しているとは言い切れません。いつでも未知の部分が残されていることを謙虚に認めるべきです。特に聖書の真理は私たちの想像をはるかに越える内容が多く、時間と共に研究が進み、考古学や歴史の事実が発見されるにつれて、さらに深い真理が明らかになってきます。早まって短絡的な結論に走るとその真理を見失ってしまいます。
- 3. 私たちはあらゆる種類の思想が入り混じった時代に生きているのです。
それゆえ、しっかりとした信仰を必要としています。21世紀は科学が進歩するだけではなく経済や思想や文化の境目がとりはずされつつある時代です。私たちの上に迫ってくるものは無神論者からの攻撃の危険だけではありません。私たち一人一人の信仰の土台が問われているのです。
今こそ自分の信仰の土台をしっかりと据えるときです。他人の土台を覆すことに熱心になるよりも、自分の信仰の土台を堅く据えることに熱心になるべきです。